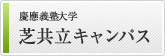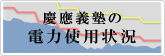慶應義塾における生成AIの利用ガイドライン
1. はじめに
1.1. 本ガイドの目的
生成AIは、学修・研究・業務の効率を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。本案内の目的は、生成AI利用時のリスクを正しく理解し、情報セキュリティを確保しながら、その恩恵を最大限に引き出すことにあります。義塾の構成員一人ひとりが内容を遵守し、責任ある利用を行うことが求められます。
なお、授業やレポート・課題等における利用については、本ガイドと合わせて、別途発信されている「慶應義塾におけるChatGPT等生成AIの利用について (2023年5月15日)」を必ず確認し、授業科目担当教員の示す方針のもとで適正に活用してください。
1.2. 対象者
義塾に在籍するすべての学生、大学院生、および教職員(一貫教育校や大学病院を含め、常勤・非常勤を問わず)
※現在、Google Workspace for Educationでは、利用規約および義塾契約下のテナント管理ルールに基づき、年齢制限等が適用されています。
2. 利用上の注意・禁止事項(全利用者共通)
各種AIサービス(法人契約内外を含める)の利用にあたっては、以下の事項を必ず遵守してください。
2.1. 情報の取り扱い
個人情報、プライバシーにかかわる情報、機密情報等の取り扱いには十分注意してください。義塾が契約する法人向けサービス(後述の3章「C」)を利用する場合でも慎重な扱いが必要であり、特に法人契約外のサービスに対しては、プロンプトやファイル添付による個人情報・機微情報の入力は行わないでください。
2.2. 適切な利用のための基本原則
- ファクトチェックの徹底: 生成AIは、事実に基づかない情報(ハルシネーション)を生成することがあります。生成された情報については、必ず一次情報(元の論文や信頼できる資料など)に基づいて裏付けを取り、事実確認(ファクトチェック)を行うことが強く推奨されます。
- 独自性・独創性の確保: 生成AIが提供する情報は、あくまで参考資料として位置づけられるべきものであり、最終的な成果物は、利用者自身の思考に基づいた内容の構築が求められます。生成された情報に対しては、自らの見解を加え、独自性・独創性を確保することが重要です。授業課題等における生成AIの利用については、「慶應義塾におけるChatGPT等生成AIの利用について (2023年5月15日)」を必ず確認し、授業科目担当教員の方針に従って適切に利用してください。
- 研究の透明性と再現性の確保: 生成AIを活用することで、画像やデータの編集・加工、要約等が容易になりますが、生成された情報をそのまま用いると意図せず研究不正に該当するおそれがあるため、十分な注意が必要です。研究の透明性や再現性を確保し、研究成果に対する責任は研究者自身が負うことを十分に理解してください。
- 各研究活動におけるルールの遵守: 生成AIを用いた成果物を研究に含める場合は、使用したAIツールやモデル、プロンプト、生成内容の出典を明示するなど、投稿先の学術誌や学会の方針に従うことが求められます。また、各研究活動においては、関係するすべての研究者が共通の生成AI利用方針を共有し、統一的な対応を図るよう努めてください。
- 著作権への配慮: 著作権で保護された論文や記事等を扱う際は、著作権法で認められた範囲(例:学習・研究目的での利用)を逸脱しないよう注意してください。利用するAIサービスによっては、取り扱った著作物が意図に反して目的外利用されるリスクが生じる可能性があります。
- 生成物の確認: 意図せず既存の著作物と酷似した表現が生成される可能性があり、既存の著作物と類似性のある生成物を著者権者から許諾を得ずに利用すると著作権侵害となります。生成された情報の利用前に類似の表現がないか確認するよう努めてください。
- 倫理的利用: 差別や偏見を助長したり、他者の名誉を毀損したり、公序良俗に反したりする目的で利用してはいけません。
3.【重要】各種AIサービスの分類と利用前提について
生成AIサービスは多岐にわたりますが、「義塾の管理下で提供されるもの」と「個人で利用するもの」では、情報セキュリティのリスクが異なります。入力した情報(個人情報・研究データ・機密情報等)を守るため、必ずこの違いをご理解ください。
| AIサービスの分類 | 【A】ライセンスフリーで利用するAIサービス (アカウント等の発行や明示的な契約を行わずに利用可能なサービス) |
【B】個人・個別契約のAIサービス (アカウント作成やライセンス契約等を行うもの) |
【C】法人全体契約に基づくAIサービス (特に慶應義塾が契約するもの) |
|---|---|---|---|
| サービスの利用形態例 | ChatGPT, Gemini, Claude等のAIサービスの内、ライセンスフリーで利用できるAIサービス群 例)サービス利用時に制約がない、もしくは、利用規約に同意するだけで利用可能となる等 |
ChatGPT, Gemini, Claude等のAIサービスの内、アカウント登録や明示的な契約を前提とするサービス群 例)利用アカウントの登録、クレジットカードによる個人課金等 |
(2025年7月現在、試行的導入) 慶應義塾の契約下で利用する Gemini, NotebookLM ※標準機能版での提供となります。 法人単位での包括契約となり、Keio.jpアカウント下で利用可能 |
| 利用データの外部流出やモデル学習へのリスク | 利用データにおいて、データ流出などのリスクも高く、AIサービスにおけるモデル学習に利用されることも懸念される | オプトアウト(利用データの外部流出の制限)が前提、もしくは選択的設定が可能なケースが主流 ※サービス毎の利用条項や設定が異なるため慎重に確認することが求められる |
デフォルトで、外部へのデータ流出やモデル学習が制限・管理される(全体としてオプトアウト制御下での利用が前提となる。) |
| 事務業務等、法人運営業務における利用 | 機微情報等の漏洩リスクを伴うため、利用を控える | 機微情報等の漏洩リスクを伴うため、利用を控える | 法人契約のサービス内の機能で利用可能 |
| 教育(授業)・研究における利用 | 教育(授業)・研究としては、利用を控える | 各AIサービス毎の利用条項において、オプトアウトの適用等、各個人、義塾における活動にリスクを伴わないことを十分に確認の上で利用する | 法人契約のサービス内の機能で利用可能 |
| 個人情報・機微情報の取り扱い | 個人情報や組織運営に関わる機微情報等の入力(プロンプト入力やファイル添付)は避ける | 個人情報や組織運営に関わる機微情報等の入力(プロンプト入力やファイル添付)は、原則避ける | 個人情報、プライバシーにかかわる情報、機密情報等の取り扱いには十分注意が必要、基本的には無用に入力(プロンプト入力やファイル添付)は行わない事が望ましい |
※「大学生限定Gemini無料アップグレード特典(15か月)」について
これは、義塾のメールアドレス (@keio.jp)を登録情報として入力することで、個人のGoogleアカウントの機能をアップグレードするものです。義塾が管理する法人契約サービス(上記のC)とは異なり、B. 個人契約のAIサービスに分類されます。利用規約等をよく確認し、上記Bに基づく注意を払ってください。(15 か月間の大学生向け特典は 2025 年 6 月 30 日に終了した旨の案内が掲載されています。最新の情報や詳細については、Google 社のページをご確認ください。)
4. 義塾提供の Gemini / NotebookLM の主な機能 (2025年7月現在で試行導入)
2025年7月時点で、慶應義塾の契約下、Google Workspace for Educationで提供されるGeminiおよびNotebookLMは、標準機能版が試行導入されており、@keio.jpからアクセスすることで法人契約に基づくAIサービスを利用することが可能です。画像生成やより高度なモデル (Gemini Advanced) など、一部の有償機能は提供できませんが、学修・研究・業務において安全に利用が可能です。
概要については「Google の AI とはじめよう」が参考になります。 詳細な操作方法については「Gemini・NotebookLMの利用について」をご参照ください。
4.1. Gemini
対話形式で、文章の作成、要約、翻訳、アイデア出し、情報検索の補助など、幅広い知的生産活動を支援します。
4.2. NotebookLM
自身がアップロードした資料(PDF、テキストファイル、Googleドキュメント等)の内容に基づいて、質問応答や要約を行うことに特化したツールです。
4.3. Google AI Studio 【!!! 利用時注意 !!!】
Googleが提供する最新の生成AIモデル(Geminiなど)を、ブラウザ上で誰でも気軽に試せる無料のウェブツールです。
本サービスの利用は、無料で提供されている機能の範囲内に限定してください。keio.jpアカウント(慶應ID)を使用して、有料機能を利用するためのクレジットカード登録は絶対に行わないでください。
もし有料機能の利用が必要となる場合は、keio.jpアカウントとは別の個人で管理されているGoogleアカウントをご利用いただきますようお願いいたします。
Google AI Studioは、慶應義塾が契約するデータ保護の対象となるサービス(「Gemini」や「NotebookLM」など)とは異なり、慶應義塾テナントのサービス対象外です。
そのため、入力されたデータは、Googleの利用規約に明記されている目的で情報が収集・使用される可能性があります。意図しない情報漏洩などを防ぐため、個人情報や機密情報といった重要情報の入力は、固くお控えくださいますようお願いいたします。
5. 責任の所在
- 生成AIは、学習・研究・業務を補助する「ツール」です。
- AIが生成した内容を、どのような形で利用し、成果物として発表するかの最終的な判断と責任は、すべて利用者本人にあります。
- AIの利用によって生じたいかなる問題(情報漏洩、著作権侵害、研究不正等)についても、慶應義塾は責任を負いかねます。利用者本人がその責任を問われることを強く認識してください。
最終更新日: 2025年12月3日
内容はここまでです。